



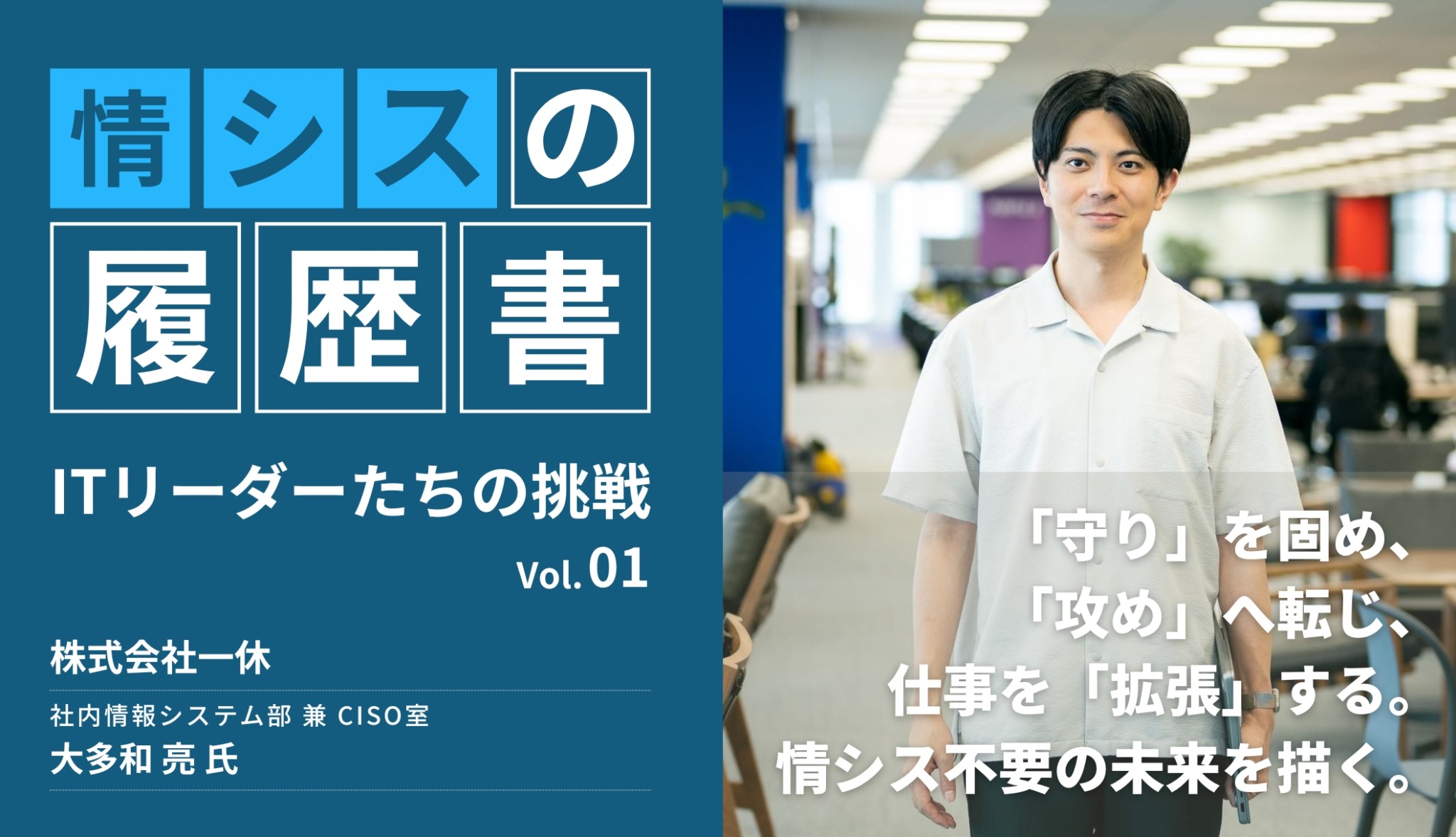
――ご経歴と株式会社一休の情シスに参画するまでの経緯をお聞かせください。
大多和さん(以下、敬称略):私は一休が2社目になります。新卒では学生時代にインターンをしていた不動産系の企業へプログラマーとして入社し、システム設計や開発などを担当しました。約3年間勤務した後、「さらに幅広い領域を手がけたい」と考え、一休へ転職しました。
当時、一休の情シスは立ち上げ直後でメンバーもごく少数。より広い領域を一気通貫で担い、経験値を高められる環境に強く引かれたのです。情シスとしての実務経験はありませんでしたが、2018年から社内情報システム部でキャリアを積み始め、現在に至ります。

株式会社一休 コーポレート本部 社内情報システム部 兼 CISO室 大多和 亮氏
――2022年からは情シスに加え、CISO室も兼務されています。その背景を教えてください。
大多和:CISO室については、自分から手を挙げました。一休では部署異動や兼務も制度を利用して希望できるので、情シスの範囲に加えてプラスアルファの取り組みを幅広くやっていきたいという思いで兼務しています。
情シスでは、ITに関わること全てを、正社員3名を中心に業務委託や常駐スタッフを含めた数名の体制で担っています。具体的には、クラウドサービスやSaaSの運用・管理、オフィスネットワークやサーバーのインフラ管理、PCやスマートフォンなどデバイスの調達・管理、さらにヘルプデスク業務まで幅広い内容です。
一方、CISO室はグループ企業であるLINEヤフー株式会社と連携しながら、情報セキュリティとガバナンスを統括しています。ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)取得・運用、DPO(データプライバシーオフィサー)対応、プロダクト側のセキュリティ対策まで、多岐にわたるセキュリティ分野をカバーしています。
――開発やシステム運用を担当するエンジニアから情シスへ転身して、仕事との向き合い方で異なる点は何だと思われますか。
大多和:一番の違いはユーザーとの距離です。SIerやプロダクト開発部門では、お客さまは一般のBtoCユーザーであり、日常的に声を聞く機会は多くありません。一方、情シスのユーザーは自社の従業員です。そのため、Slackやメール、口頭で即座にフィードバックが届きます。顔の見える距離でコミュニケーションを取りながら、改善サイクルを回す必要があります。
――株式会社一休は「ユーザーファースト」の理念を掲げています。情シスの立場では、どのように解釈していますか。
大多和:当社が掲げるユーザーファーストは本来サービス利用者に向けた理念ですが、情シス視点では従業員こそがユーザーです。従業員の業務が滞りなく進むIT環境を整えることがミッションだと考えています。
その上で大切にしている価値観は、組織や担当業務の枠を極力設けないことです。CISO室だからセキュリティだけ、情シスだからITだけという線引きをせず、人事・総務・法務など他部門の業務範囲にも積極的に関与する姿勢を大切にしています。
――その価値観はどのような経験から培われたのでしょうか。
大多和:転職時の考え方とも共通しますが、「1つの領域に閉じず、幅広く対応できるビジネスパーソンになりたい」という思いが原点です。情シスの職域を超越し、プラスアルファの貢献を続けることで組織の壁を越える働き方を意識しています。
最近では社内稟議システムのリプレイスにも関わりました。従来は法務や経理が導入したシステムでしたが、情シス視点での連携が必要だったため、製品選定からテスト、稟議フロー設計、社内説明会まで一貫して担当し、法務・経理と連携しながら進めました。また、36協定の従業員代表や衛生委員会にも手を挙げ、労務・総務領域にも関与しています。これにより、従業員が働きやすい環境づくりに直接携わることができ、バックオフィス業務全般での貢献も意識しています。
――従業員とのコミュニケーションを円滑にするため、どのような工夫をされていますか。
大多和:私はオフィスで働くのが好きなタイプなので、対面コミュニケーションを重視したランチや雑談の場での交流を大切にしています。加えて、部活や飲み会の企画にもできるだけ顔を出し、業務外のつながりを通じて直接ヒアリングできる関係性を築いています。
部活については、会社からもコミュニケーションの活発化を図る活動として、手当などの支援をしてもらって活動しています。スポーツ系から文化系までジャンルは多彩で、Slack上のチャンネルを起点に自由に参加できる形式です。コーポレート本部や営業部門など、日頃は接点の少ないメンバーと交流できる機会になっています。

日々のリアルなコミュニケーションを大切にすることで、身近な情シスであることを心がけている
――大多和さんはどの部活に携わっているのですか。
大多和:現在はサウナ部の部長として、サウナ好きの従業員をSlackに招待し交流を行っています。他にも興味を持った部活には一通り参加し、部署を超えた関係づくりにも力を注いでいます。こうした活動はもともと好きで、前職でも社内の委員会に所属していましたし、学生時代から課外活動や講演活動に積極的に関わってきました。
――上長である CISO がデータサイエンス部・CTO室と兼務していると伺いました。
大多和:情シスは全ての部署と関わります。データサイエンス部とも日常的にコミュニケーションを取っています。守りの面では、データサイエンス部が利用するサーバーやデータベースの更新に情シスとして関与しています。攻めの面では、データサイエンスのエンジニアがつくった営業向けの開発ツールを情シス側でMDMを通じて配信するなど、仕組みづくりを担当しています。
――少人数で多岐にわたる活動をこなす中、省力化はどのように進めていますか。
大多和:キッティングなどのルーティン業務は徹底して自動化し、人が介在すべき入社時オリエンテーションや新人教育は対面で行うといった切り分けをしています。PCセットアップやアカウント発行などのクリエーティブではない業務は自動化を進め、人間が関わらなくても済む状態を目指したいと考えています。
――外部パートナーとの業務分担や将来的な体制像についても教えてください。
大多和:業務委託の方には担当範囲を明確にし、例えばヘルプデスクならヘルプデスクに専念していただくようお願いしています。最近は業務委託や派遣スタッフを減らしており、将来的には外部パートナーの手を借りなくても回る体制を目指しています。最終的な理想は、情シスという部署自体がなくても全社業務が回る状態です。情シスの人数が減ればもちろんコストも減りますから、そこを最小化することが理想だと考えています。そのためにも、日々自動化を進めています。
――最後に、今後のキャリアの展望や、現在感じている課題や取り組みたいテーマを教えてください。
大多和:コーポレート本部の幅広い業務を担うのはもちろん、事業側にも踏み込みたいと考えています。情シスの枠を超えて、より大きな付加価値を提供できる存在になることが目標です。そのためにも、省力化はキャリアを広げるための前提条件だと捉えています。チームのメンバーも同じ志を持っていると自負していますので、情シスの部門としてさらなる成長を目指していきたいです。
一休の情シスとしては、守りと攻めの二軸で展望を考えています。まず守りの面では、情報漏えい対策の強化が最優先です。昨今は、社会全体でサイバー攻撃の手口がますます高度化・巧妙化しており、組織の規模や業種を問わず、従業員が悪意なく機密情報を外部に流出させてしまうリスクが高まっていると感じています。当社においても、テクノロジーを活用した防御策と、教育を含めた人的施策を組み合わせ、セキュリティ体制を高めていきたいです。
一方、攻めの面ではAI活用が重要なテーマだと考えています。エンジニアだけでなく、事業側や人事・広報・総務などバックオフィスでもAIは不可欠なツールになりつつあります。誰もが安心して利用できる基盤を整えることに加え、利用方法が分からない従業員に寄り添い、伴走しながら活用の幅を広げていきたいと考えています。
インタビューを通じて見えてきたのは、まさに「守り」の哲学を土台に、「攻め」の施策を打ち、自らの仕事を「拡張」し続けてきた大多和氏のキャリアそのものであった。そして、その先に見据える「情シス不要の未来」という逆説的なゴールこそ、究極のユーザーファーストであり、会社の未来をつくるITリーダーの一つの姿なのかもしれない。(情シスのじかん編集部)

大多和 亮 氏
株式会社一休 コーポレート本部 社内情報システム部 兼 CISO室
2015年、大手企業の情報システム部門で社内SEとしてキャリアを開始。基幹システムの保守運用・開発を経て、2018年に株式会社一休に入社。2022年よりCISO室を兼務し、情報セキュリティとデータプライバシー領域も管掌する。並行してスタートアップ企業の支援や、ITカンファレンス「BTCONJP」運営を実施。加えて、記事寄稿・イベント登壇を重ねるなど、実践知の発信にも注力している。
■株式会社一休について
株式会社一休は、「こころに贅沢させよう」をコンセプトに、宿泊予約サイト「一休.com」をはじめ、レストラン・スパ予約など上質な体験を提供するサービスを展開する企業である。大多和氏のように、職域を限定せず、高い視座で価値を生む姿勢に共感を覚えた方は、同社の採用ページを確認してみるとよいだろう。
執筆:七瀬ユウ
新卒で大手Slerに入社し、基幹システムの開発・プロジェクトマネジメント業務に従事。WEB広告企業でセールスライターの経験を経て、2021年にWebライターとして独立。オウンドメディアのSEO記事制作や、SNS運用代行、Kindleプロデュースなどを担う。情シスのじかんでは企画立案から執筆、編集を担当。
(編集:稲垣章 PHOTO:野口岳彦)
30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

