



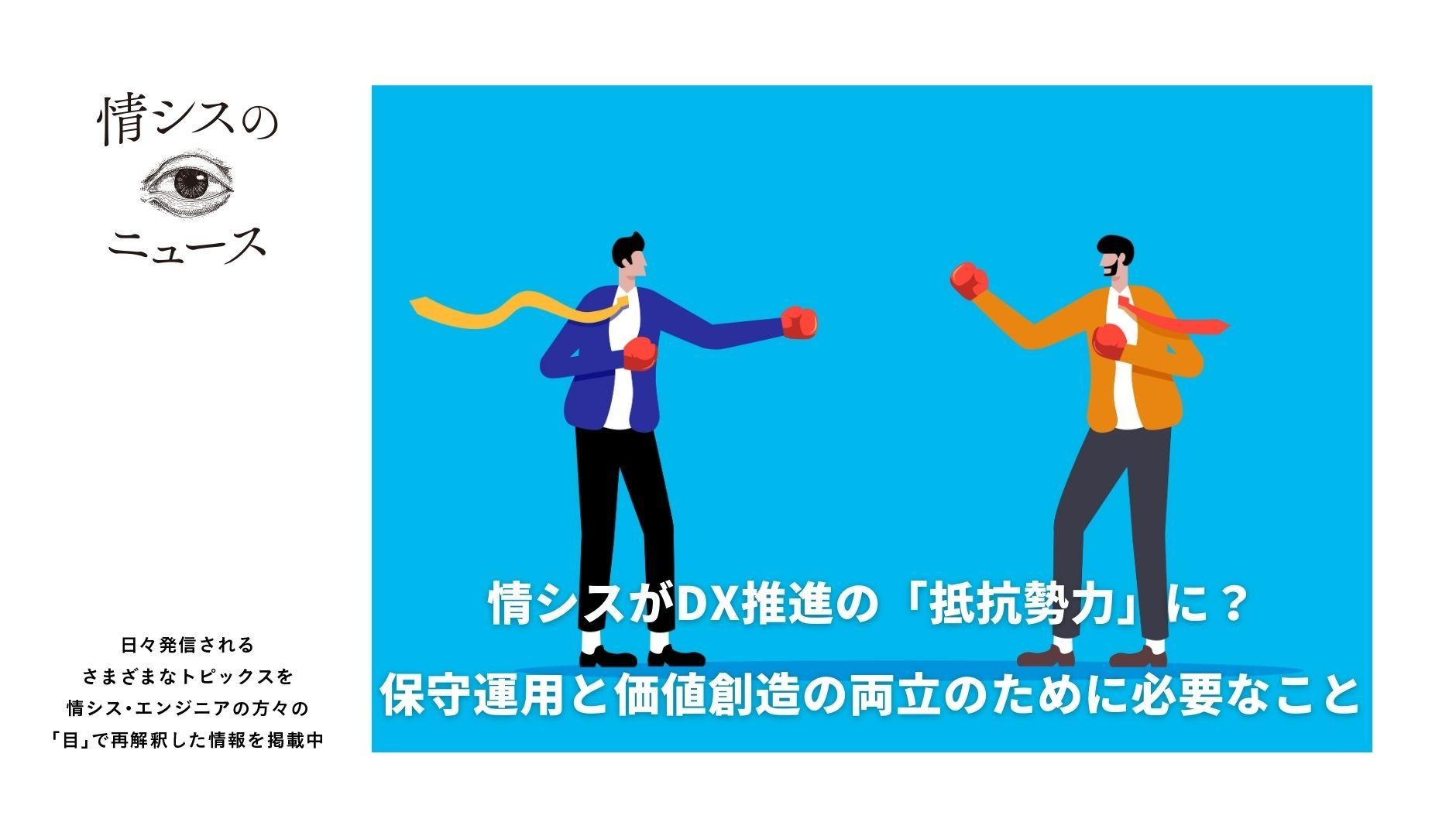
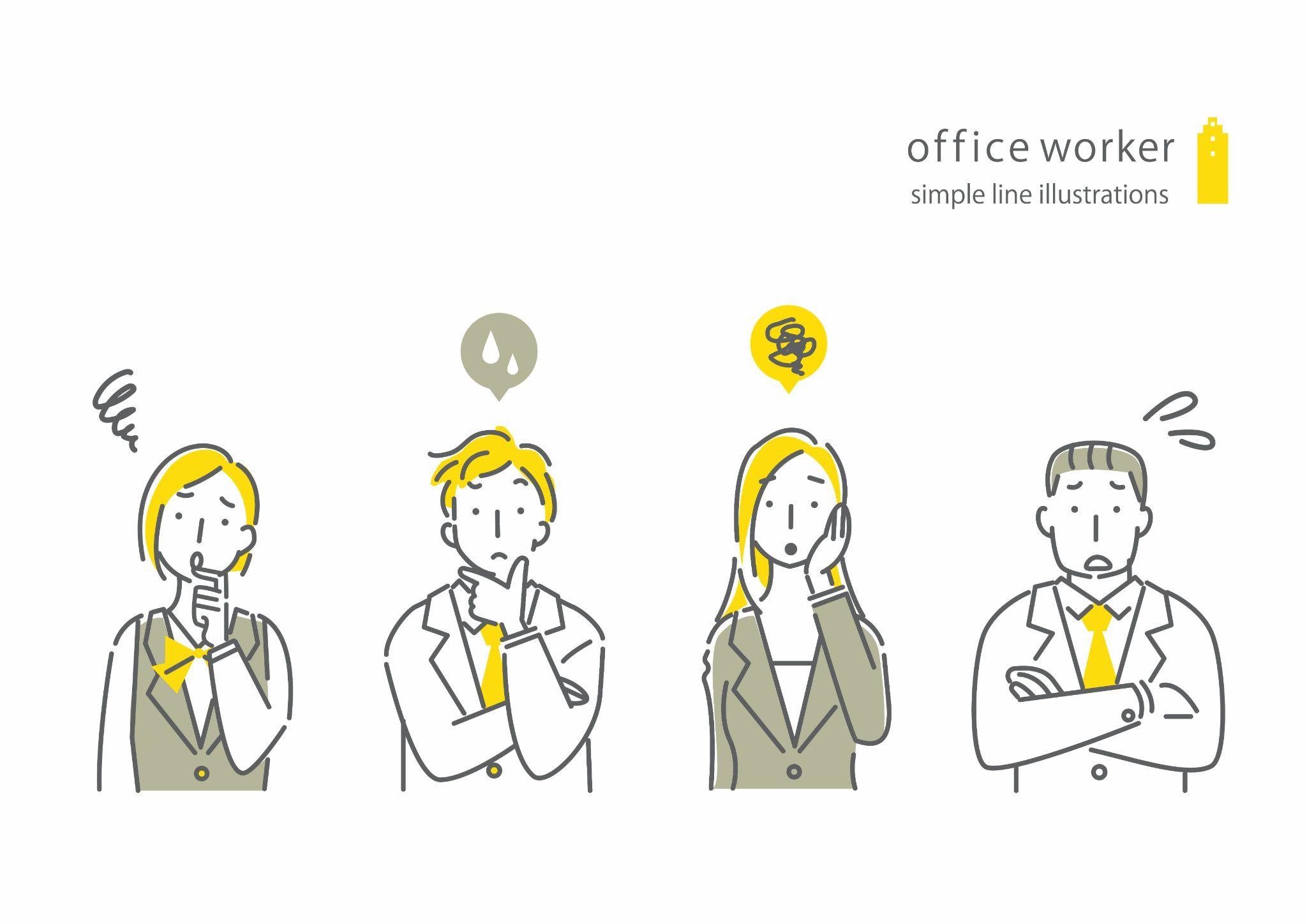
運用・保守に集中する情シスの構造的課題は保守重視の姿勢と、情シスの「モード」の違いにあります。
多くの中小企業では、情シスの業務リソースの大半が既存システムの維持管理に割かれており、新たなIT投資に充てられる割合はごくわずかです。実際、ある調査(※1)では企業のIT予算配分において「現行業務の維持・運営」に80%以上を費やす企業が全体の66.3%に上り、「ビジネス変革のための投資」が20%未満に留まる企業も45.8%に達するといいます。
このような保守重視の体制では、新しいシステム開発やDXプロジェクトに振り向ける時間・予算が確保できず、結果的に社内には停滞感が生まれます。加えて、中堅・中小では「ひとり情シス」(担当者が一人だけ)や「ゼロ情シス」(専門部署がない)といった状況も珍しくなく、少人数で日常業務に追われるあまり戦略的なIT活用に踏み切れない要因となっています。
情シスが守りの業務に追われている限り、DX推進の起爆剤となる「攻めのIT」にリソースを振り向けることは難しく、企業全体としてデジタル変革が進みにくいのです。
「守りのIT」と「攻めのIT」とは具体的に何が違うのでしょうか。ガートナーが提唱したバイモーダルITの概念では、ITの役割をモード1とモード2という二種類に分けて考えます。「モード1」はシステムの安定性や効率化(SoR:System of Record)を重視し、「モード2」はビジネスの俊敏性や革新(SoE:System of Engagement)を重視する手法です。
モード1に分類されるシステムの典型例は人事・会計・生産管理など基幹業務システムで、高品質・安定稼働や手厚いサポートが求められ、主眼は業務効率化によるコスト削減にあります。一方のモード2は、顧客向けのデジタルサービスや社内業務のデジタル化プロジェクトなどが該当し、迅速な開発・改善や使い勝手の良さといった俊敏性・柔軟性が重視されます。
いわばモード1は「守り」、モード2は「攻め」のITと言え、それぞれ求められるスキルや文化も大きく異なります。 情シスがDX推進を担うには、このモード1・モード2双方の視点を持つことが不可欠です。

高騰するERPやSI費用に悩む中、情報の蓄積と組織の学習が必要です。
DXを進めるにあたり、まず情シスが取り組むべきは「車輪の再発明」を避けることです。同じ機能や仕組みを一から開発し直すのは、時間とコストの無駄につながります。情シスは社内外に蓄積された情報資産をフルに活かし、重複作業を減らすマネジメントが求められます。
例えば、過去のプロジェクトで得た知見や開発したモジュールはドキュメントやナレッジベースに整理し、次の開発では再利用することで知的生産性を高めることができます。社内の「組織的な学習」を促進することもポイントです。情シス内で定期的に振り返り(レビュー)を行い、成功事例や失敗から得た教訓を共有することで、組織全体の知見が蓄積します。一度きりのプロジェクトで終わらせず、学習するIT組織へと進化することが、無駄を省きDXを前進させる原動力となるでしょう。
DXを成功させる最大の鍵は「人」です。いくら最新技術を導入しても、それを使いこなしビジネスに活かす人材がいなければ絵に描いた餅になってしまいます。したがって「人材育成なくしてDXなし」というのは多くの専門家が指摘するところです。情シス業務として「人材育成・教育」に時間を割く企業が急増しています。
情シス人員の不足に対して「社内で育成する」が対策の第1位に挙げられたという結果※3もあり、企業がDX人材の育成に本腰を入れ始めていることがうかがえます。 中小企業の情シスが目指すべき人材像とは、ITスキルと業務理解を兼ね備えた「デジタル人材」です。ただシステムを管理・運用するだけでなく、業務部門と対話しながら課題を発見しテクノロジーで解決策を提案できるようなスキルセットが求められます。
また、マインドセットの面でも転換が必要です。変化の激しいDXの時代には、「決められたことを確実にこなす」姿勢(モード1型)だけではなく、「まず小さく試し、失敗から学んで素早く改善する」姿勢(モード2型)が重要です。
ここまで述べてきたように、情シスとDX推進のキーワードは「モード1(守り)とモード2(攻め)の両立」です。中小企業の情シスが企業価値向上に貢献するには、現行システムの安定運用という足場(ベース)を固めつつ、新たなデジタル施策という車輪をもう一つ回し始める必要があります。
両輪のバランスを取るための戦略としては、例えば定型的な保守作業の自動化・アウトソーシングを進め、情シスの手が空いた分をDX企画に充てるといった方法が考えられます。また、経営層に対して情シスが単なるコストセンターではなくビジネスの推進役たり得ることを訴求し、経営の理解と後押しを得ることも重要です。組織が小さい中小企業では専任チームを二つに分けるのは難しいかもしれませんが、だからこそ一人ひとりが二つの視点を持つ意識改革が求められます。
日中はモード1業務で忙しくとも、例えば週に数時間でもモード2的な改善提案の時間を設けるなど、小さな工夫で両輪を回す第一歩を踏み出せるでしょう。
中小企業情シスの未来戦略として重要なのは「守り」と「攻め」の両立、そして人と知恵への投資です。保守運用で培った信頼性を土台に、新しいデジタル技術への挑戦を恐れず続けることで、情シスは企業の成長戦略に欠かせない存在へと進化できるでしょう。
小さな一歩の積み重ねがやがて大きな変革につながります。情シスが主体的にDX推進の舵を握り、モード1・2を巧みに使い分けながらしなやかに進化する組織を目指すことこそ、中小企業が次のステージへ踏み出す鍵となるのです。
著者:犬を飼っているゴリラ
大手IT企業に入社し、フロントエンド、PFシステムの開発に従事。その後、IaaSサービスなどの各種サービス事業開発に携わったのち、大手HR・販促事業会社に転職した。2018年にMBAを取得し、現在も国内大手メーカーの新規事業企画、プロダクトオーナーなどを担っている。
(TEXT:犬を飼っているゴリラ、編集:藤冨啓之)
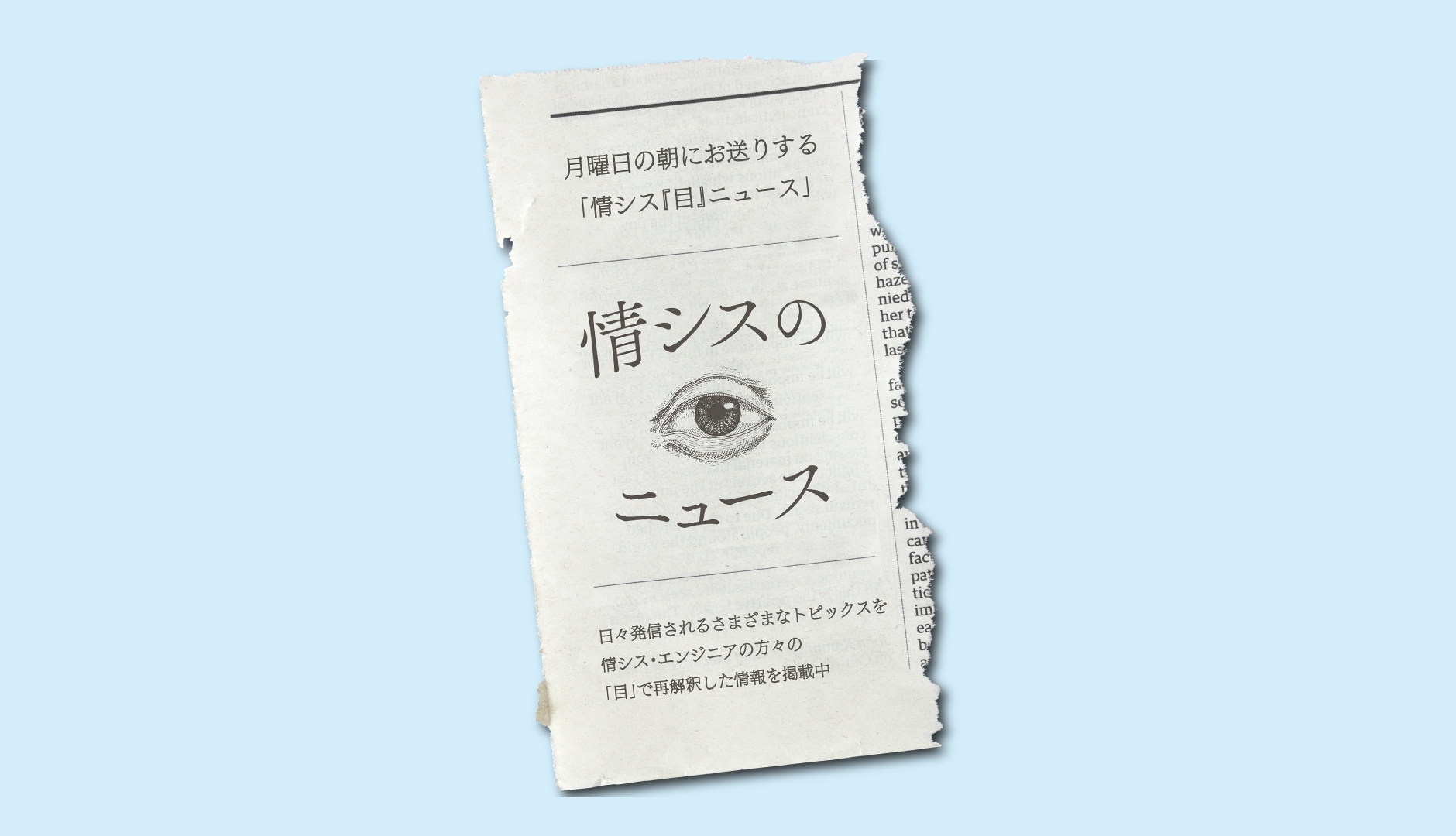
月曜日の朝にお送りする「情シス『目』ニュース」では、日々発信されるさまざまなトピックスを情シス・エンジニアの方々向けに「再解釈」した情報を掲載中。AI、働き方、経済など幅広いニュースをピックアップし、業務に役立つほか、つい同僚に話したくなる面白い話題まで身近で自分事化しやすくお届けします。
本特集はこちら30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

